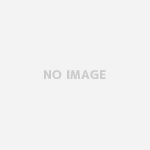給料から税金や保険料などの差っ引かれる金額の簡単な計算方法法をお伝えします。
この計算をすることによって、自分の税額にあった節税方法を実施してみてください。
具体的に一例で言うと
住宅ローン控除のような所得税額から控除されるような制度を利用する時の計算に使ってください。
損しないための税金優遇制度 住宅ローン控除編
で詳しく書いています。
1.給与から引かれる正体
給与から絶対引かれる金額
社会保険料
1.厚生年金保険料
2-1.健康保険料
2-2介護保険料(40歳以上)
3.雇用保険料
税金
4.住民税
5-1.所得税
5-2.所得税に掛かる復興特別所得税
この順番で計算していきましょう。
なぜかと言うと、4.5の税金は、社会保険料を控除した額に掛かってくるからです。
2.社会保険料の計算

月収とボーナスに掛かってきます。
1.厚生年金保険料
厚生年金の実施機関は、会社員であれば日本年金基金、公務員や教職員は共済組合です。
一般的な日本年金基金の例で説明していきます。
仕組みは一緒ですので安心してください。
全31等級に区分される「標準報酬月額」(月収)と「標準賞与額」(ボーナス)をもとに計算します。
1等級8万8千円~31等級62万円
計算式
上記の額に9.15%を掛けた額です。
月収とボーナスともに引かれます。
「標準報酬月収」とは
4月、5月、6月の平均の給与を平均した金額をその年の9月から翌年の8月まで計算するための給与としての基準にする額です。
※この給与には、役職手当、住宅手当、通勤費、残業代など総支給額のほとんどを合算します。
4,5,6月に残業しまくると保険料が上がります。
ただし、2等級以上を三か月続けて上下すると再計算されます。(この時は、通勤費、残業代などは含めません)
「標準賞与額」とは
一時金として支給される報酬に掛かります。(上限は150万円)
1000円以下の単位は切り捨てられます。
一覧できっちり確認したい人は下記の「日本年金機構」のホームページから確認してください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/20170822.html
ざっくりで良い人は、月収に9.15%を掛けてください。
明細によっては標準報酬月額が記載されていることもあります。
2-1健康保険料 2-2介護保険料
会社員の健康保険は「協会けんぽ」(都道府県ごとに金額に違いがある)と「組合健保」(会社ごとに金額の差あり)があります。
組合健保は、主に大手企業がメインです。(独立した組合)
公務員は、共済組合に加入します。
51等級に区分されます。
1等級5万8千円~50等級139万円
こちらも一覧で金額を確認できます。
表の金額にあてはめるだけです。
※賞与は1000円以下を切り捨てて各都道府県の保険料率を掛けましょう
全国保険協会ホームページURL
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou3gatukara/
ざっくり計算
月収や賞与に40歳以下は10%を掛けてください。(東京は9%台)
月収や賞与に40歳以下は12%を掛けてください。(東京は11%台)
※各都道府県にムラがあるので確認したほうが良いです。
10%は結構な比率です。
3.雇用保険料
厚生労働省の管轄です。
こちらは総支給額を用いて計算します。
※標準報酬月額ではなく、残業代や住宅手当を含んだ総額です。
業種によって保険料率が少し違います。
ざっくり計算式
一般の事業 総収入×0.3%
農林水産・清酒製造業 総収入×0.4%
建設業 総収入×0.4%
社会保険料だけですでに20%前後引かれていますね。
単純に12か月で240%が引かれています。2.5か月分は社会保険料の為に働いているわけです。
ボーナスまで考えたらゾッとします。
税金
税金の計算には控除があるので、少し計算を繰り返しますが簡単です。
2020年1月以降 (最新)
4.所得税
収入があった時に掛かる税金です。
給与だけでなく、例えば株に投資して儲かっても掛かりますし、貯金の金利にもかかります。
基本的に、何かの収入があれば掛かります。一部非課税のものもあります。
収入が上がるほど税額が増えます。
毎月徴収されていく点は、社会保険料と同じですが、所得控除というモノがあります。
年末調整という言葉は聞いた事があると思います。
この年末調整というのは、年末に毎月収めた税金から、一年間の控除額を引いて払いすぎていたら返してくれる仕組みです。
毎月の引かれる税金と年収ベースでの課税額を出していきましょう。
課税所得×給与所得税率で税額は出ます。
分かりやすく説明していきます。
月収
総収入に対して「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて税額を出します。
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_1.htm
検索窓に「給与所得の源泉徴収税額表」をコピペして検索したすぐ出ます。
年収・年末調整(簡単な流れ)
収入ー所得控除=課税所得
↓
2.課税所得×税率
↓
毎月払った所得税ー年末に再計算した所得税=払いすぎた税金の還付
具体的に分かりやすく説明します。(2020年1月制度改正後)
(年収にあたる収入)-(下記表に当てはめた金額)=A
Aー(社会保険料)ー(生命保険控除など)-(基礎控除48万円)=課税所得
復興特別所得税 102.1%を掛けてお終い。
給与所得控除 表
| 給与等の収入金額 | 控除額 | 備考(控除) |
|---|---|---|
| 180万円以下 | 収入金額×40%ー10万円 | 55万円に満たない場合は55万円 |
| 180万円~360万円 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 360万円~660万円 | 収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円~850万円 | 収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円以上 | 195万円(上限) |
課税所得×下記税率表=所得税
所得税の税率表
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円~1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1800万円~4000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
少し手間ですが当てはめるのと、足し算と引き算ができたら楽勝です。
住民税
所得税と計算は似ています。
控除後所得ー基礎控除(43万円)
A×10%(一律)+5000円=次年度の住民税額
次年度の住民税×102.1%=復興特別所得税込み
この金額を12等分すれば月々の金額です。
ざっくり実際に計算してみましょう

35歳 独身 東京在住者 保険など何も入っていない
月収30万円 賞与50万円×2回 年収460万
住民税は前年度の基礎控除33万円を使用
| 月収 保険料・税額 | 賞与 保険料・税額(2回) | 年額 | 年末調整 | |
|---|---|---|---|---|
| 厚生年金保険 | 27,450円 | 49,350円(98,700円) | 428,100円 | |
| 健康保険 | 14,805円 | 45,750円(91,500円 | 269,160円 | |
| 雇用保険 | 1,050円 | 1,500円(3,000円) | 15,600円 | |
| 所得税 | 6,750円 | 16,750円(33,500円) | 114,500円 | 71,385円 |
| 住民税・復興特別所得税 | 25,151円 | 0 | 301,813円 | |
| 合計 | 224,794円 | 113,350円(226,700円) | 1,129,173円 | |
| 手取り | 224808 | 386650円(773,300円) | 3,474,828円 | 43115円(還付) |
すっごいざっくり計算してます。
てどりがかなり寂しいことになりました。
所得が上がるともっと引かれます。
まとめ

ここまで計算方法を説明しましたが、実際は総務部や経理が計算してくれますので、出来なくても問題ないです。
大事なことは頑張って働いた給料が、どんどん減っていることに気づいてもらいと思い書き上げました。
少しでも自分で稼いだお金を直接的に使えたら良いですよね。
もちろん社会の為になるだろうお金なので、仕方ないですし、義務ですので脱税はしてはいけません。
合法的に節税をしたり、税金の低いところで稼ぐなど考える時代にきています。
そんな方法をこれからお伝えしていくつもりなのでお楽しみにー。
自己紹介
ニックネーム:ぼむ
年齢 :30代半ば
性別 :男性
転職を三回して、不動産、アパレル、金融関係を経験して、今なおサラリーマンをしながら日々資産形成や副業、支出を減らす方法を考えながらブログを書いています。
私が学んだことを、たくさんの人に広げるためにブログを始めたおせっかいな人です。