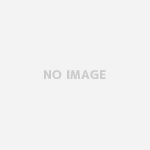会社員の人で給料のわりに手取り少ないんじゃないの?と思われる方も多いと思います。
総支給額から何が引かれていて、どんな基準で金額が決まるのかを簡単にまとめていきます。
給与から控除(引かれる)税金や社会保険料など
1.所得税・住民税
2.社会保険料(健康保険料・介護保険料など)
3.社会保険料(年金保険料)
基本的にはこの3つの金額が総支給額から引かれていくのです。
※財形制度や持ち株会などは自分で入っていることなので省きます。
また機会があったら書かせていただきます。
年収は上がったけど生活が楽にならない原因はこれらで手取り額を圧迫されているためです。
分かりやすく概要をまとめますので、もっと詳しく知りたい方は厚生労働省のホームページに詳しく難しく書いてます。
内容的に省きにくい部分も多いので簡単に説明していきますが、3部作になりそうです。
今回の記事は1.所得税と住民税について書きます。
所得税

給与所得や事業所得(営業手当など)に掛かる税金で会社が計算をして給与から自動的に引かれる税金です。
事業所得に関しては確定申告をして経費がある場合には申告しないといけません。
ここでは一般的な給与所得に関して解説します。
所得税と住民税は収入に応じて納める額が変わる「超過累進課税」を採用しています。
給料が増えれば税金も上がるという労度意欲を失くすような仕組みになっています。
概要
所得税は1月1日から12月31日の期間に得た収入に対して掛かってきます。
給与所得には給与と賞与も含まれる点と現物支給されたモノにもかかってきます。
例えば仕事頑張ったから商品券を貰ったとか高級ボールペンを貰っても税金を納めないといけませんし、居住する家賃を会社に出してもらっても所得税に対象になります。
また、基本的に会社から給料をもらっている人は確定申告は不要です。
※確定申告が必要になる人
年収が2000万円を超える人は年末調整でなく確定申告をしてください。
ざっくりと、税金の仕組みを簡単に分かりやすく説明します。
細かく説明すると個人の条件などによって控除があったり、なかったりして複雑になるので簡単な仕組み程度で説明します。
所得税に関する必要な用語
・課税所得
給料から控除額(税金が掛からない金額)を引いた金額
税金の計算の基になる金額
・給与所得
給料の金額
・給与所得控除
給料の金額に応じた控除
・所得控除
控除前の年収24000万以下の場合、一律48万控除されます
※2020年現在
を使って計算していきます。
一般的な計算式と計算表
給与所得ー給与所得控除ー所得控除=課税所得
課税所得×税率=所得税
※家族構成や住宅ローンなどによりもっと下がったりします。
下記の計算表に当てはめましょう。
給与所得控除 表
| 給与等の収入金額 | 控除額 | 備考(控除) |
|---|---|---|
| 180万円以下 | 収入金額×40%ー10万円 | 55万円に満たない場合は55万円 |
| 180万円~360万円 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 360万円~660万円 | 収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円~850万円 | 収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円以上 | 195万円(上限) |
所得税の税率表
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円~1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1800万円~4000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
この表の計算式に自分の給与を当てはめるだけで所得税額が分かります。
実際に計算してみしょう
例1
総支給が600万円の給与を貰っている人(交通費は非課税範囲内で除外)
※生命保険料控除などが無い場合
ステップ1 給与所得控除計算
600万円×20%+44万円=164万円
ステップ2 課税所得計算
600万円(給与所得)-164万円(給与所得控除)-48万円(所得控除)=388万円(課税所得)
ステップ3 所得税計算
388万×20%-42万7千円=34.9万円/年
600万円ー34.9万円=565.1万円が残ります。
こんな感じでざっくりと所得税額が出せます。
生命保険い加入していたり、配偶者が扶養家族になっている場合などは控除としてここから引いてくれます。
個人住民税

住まずは住民税の概要から
前年の所得に対して、その年の1月1日現在における(都)道府県及び市町村が決定する税金。
簡単いううと、
前年度稼いだ分に対して住んでいる(都)道府県に納める税金と市町村に納める税金ってことです。
※生活保護を受けている人や障碍者、未成年者や寡婦(配偶者を失くした人)などで前年度所得が125万円以下の人には課税されません。
個人住民税の種類と税額計算
⓵均等割り
所得金額にかかわらずに一律1500円と3500円の年額5000円が税額です。
東北の震災で500円ずつ令和5年まで増えています。
※都道府県によっては、別途税金が掛かる地域もあります。
例:京都府 「豊かな森林を育てる府民税」600円など
⓶所得割
その年の1月1日時点において、その(都)道府県および市町村に住所を有していて一定以上の所得がある納税義務者の資力(担税力)に応じてされる部分
課税所得の10%が納税額です。
下記表が内訳
| (都)道府民県民税 | 市町村民税 | 合計 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 均等割 | 1500円 | 3500円 | 5000円 | 地域によって別途有り |
| 所得割 | 4% | 6% | 10% | 課税所得に対して |
⓷利子割
こちらに関しては預金の利子などに掛かります。(税率5%)
⓵、⓶に関して会社員や公務員であれば給与から分割で天引きされます。
実際に計算してみよう
年収600万円
課税所得388万円
課税所得の出し方は、前章の所得税を見てください。
388万円×10%+5000円 =39.3万円 / 年
結構取られますよねー。義務だから払うしかないですね。
控除一覧
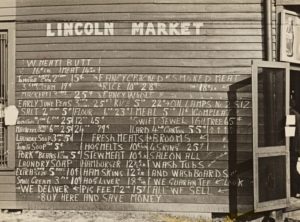
先ほどちらっと触れました控除の代表的なものを紹介していきます。
課税所得から引ける頼もしい奴です。
種類が
たくさんあるので代表的なものをダーッと解説していきます。
物的控除
〇雑損駆除
納税者や生計を一にする親族等が災害、盗難、横領などにより成果に必要な住宅や家財、現金などの資産に損失を受けた場合に認められる。
控除額
損失額-総所得金額の合計額×10%
災害関連支出-5万円
〇医療費控除
納税者と納税者と生計を一にする配偶者・親族に支払った医療費の一定額を控除できる。
※確定申告が必要
控除額(上限200万円)
(医療費-保険金(保険医加入している場合))-(総所得金額の合計×5%と10万円どちらか低い方)
〇社会保険料控除
社会保険料として支払った全額が控除対象
公的年金・健康保険料など
〇寄付金控除(寄付金の額が2000円以上)
国税庁の認定NPO法人にたいしての寄付の一定額が確定申告により控除されます。
使途が分からない税金を支払うより寄付したいよーって人にはお勧めです。
〇小規模企業共済掛金控除
全額が控除対象です。
〇生命保険料控除
2020年3月現在は
生命保険料控除 4万円
介護保険料控除 4万円
個人年金保険控除 4万円
最大合計12万円が控除されます。
〇地震保険料控除
保険料(上限5万円)が全額控除
人的控除
〇配偶者控除
本人の合計所得金額が1000万円以下でかつ配偶者の合計所得が48万円以下(給与103万円以下)の場合
本人の年収によって金額が異なります。
900万以下なら38万円
〇扶養控除
納税者と生計を一にする扶養親族がいる場合
16歳から19歳の子(一般扶養親族)
38万円
19歳以上~23歳未満の子(特別扶養親族)
63万円
同居の70歳以上(老人扶養親族)
58万円
同居以外の70歳以上
48万円
〇寡婦(寡夫)控除
配偶者と死別または離婚した者で、生計をともにする子がいる場合。
ちなみに寡(ヤモメ)と読み、語源は屋ヲ守ル女
一人で家を守る女から来ているとかです。
無駄な雑学挟みました。笑
〇勤労学生控除
働きながら学校に通う者で合計所得が65万円以下で自分の労働以外の所得が10万円以下の場合に27万円の控除。
〇障害者控除
本人または配偶者、扶養家族が一般障害者の場合に27万円。
特別障害者の場合は40万円
同居の特別障害者の場合は控除額が75万円です。
基礎控除48万円
税額控除
〇住宅ローン控除
損しないための税金優遇制度 住宅ローン控除編
上記で詳しく書いてます。
などがあります。
〇配当控除
課税総所得1000万円以下 配当金額×10%
課税総所得1000万円以上の場合
1000万円超の部分 配当金×5%
1000万円以下の部分 配当金×10%
などがあります。
まとめ

最後に所得税と個人住民税についてのまとめと感想をします。
なんとなく引かれている税金の仕組みを理解してもらえましたか?
こうやって解説をしてきて気づいた方もいるかもしれませんが、税金を少しでも減らすカギになるのは、所得控除をいかに上手に使うかです。
テレビやニュースで脱税なんかをしている人がいますが、犯罪ですし罰金及び普通に逮捕されます。
そんなことしなくても制度の知識があれば何もしない人よりも手元に残る資産を増やすことができます。
結婚をしていない人が、節税のために配偶者を作るのは難しいですし、家を買うのも難しいですが、掛け損のしない生命保険を探して入れば生命保険料控除が使えます。
少しずつ知識を付けてご自身の所得を上げてみなさんの生活が豊かになるお手伝いができれば幸いです。